昭和24年、平塚らいてうは「陰陽の調和」というエッセイで、『美しい暮しの手帖』第2号に初登場。
らいてうが疎開して生活をしていた地に、家庭料理の第一人者、中江百合が訪ねてきたときに、うれしさにこの日ばかりは、大いに腕によりをかけて、料理で歓迎したことが書かれています。
中江百合の執筆した、家庭料理のコツや楽しみを記した「お料理いろはかるた」や、「にほん料理おさらえ帖」なども『暮しの手帖』の名物記事です。
中江百合をもてなした胡麻じるこ
「家の前を流れる利根川のメソ(小さなウナギのこと)の蒲焼き、河原の野草のあえもの、自家づくりの辛味噌のおつけ、例の玄米飯といったような食養料理。
そのときこれは中江夫人がお好きそうなと思ってこしらえた胡麻じるこが、果たしてたいへんお気に入り、今でもまだ時折その話をして下さる。この胡麻じるこは格別なもの、わたくしももちろん大好きである。」
「東京へ帰ってからは、なかなか胡麻じるこでもなく過ごしていたが、同じようなしるこ店のいくつも出来るこの頃、何処かに一つぐらい本ものの胡麻じるこを食べさせる店はできないものか」 (平塚らいてう 陰陽の調和)
後日、このエッセイを読んだ友人や読者から「胡麻じるこの作り方を教えてほしい」という問い合わせが多くあり、第4号で作り方を披露したエッセイを書いています。
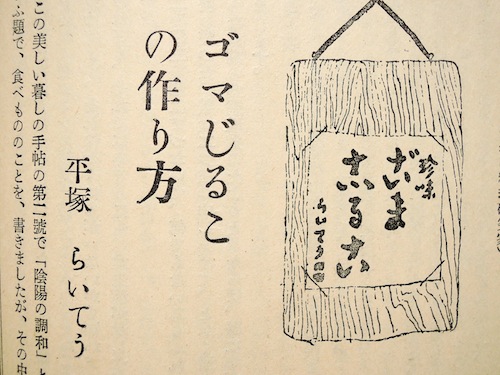
ゴマじるこの作り方 平塚らいてう
作り方の手順は、
①まず、黒ゴマを焦がさないよう注意して炒ります。
「弱火でグズグズ炒ったのでは、香りがたたないので、強火で、パチパチはねさせて手ばしっこく」炒り上げます。
②それを乾いたすり鉢で十分にすります。
③ゴマが黒々とつややかに、滑らかになったら、ぬるま湯でのばす。
④黒砂糖と塩少々で味をつける
とにかく、ゴマじるこ作りのポイントは、丹念に、丹念にゴマをすることのようです。
「すっていますとだんだんゴマから油が出てきて、とても堅く、すりこぎが廻りにくくなり、汗が出てくるほど骨がおれますが、そこをがまんして、丹念にすって、すって、すりつづけます。
ですから、わたくしのようなものには苦が手ですが、奥村は実に持ち前の熱意と気長さとで、代わってやってくれます。そばで、わたくしがもういい頃でしょうと、何度か言葉をかけてもなかなか聞いてくれません。」(第4号 ゴマじるこの作り方より)

伊豆土肥温泉にて 平塚らいてうと奥村博史 1914年
オニキスのような光沢が出るまで
「それだけに、わたくしのところでつくる ゴマじるこ はすばらしい出来栄えで、奥村にいわせればオニキスのような光沢(つや)が出るまですらなければ、これは本当の味覚は得られないというのですが、つまりよく、よくするということが ゴマじるこ を上手に作る唯一の秘訣なのです。」
ブラックオニキスのような光沢というのは、指環の制作も手がけていた奥村博史らしい表現です。
すり続けたゴマの出来を表していますが、すりづらいからと早く水を加えてしまうと、キメがあらくなり、取り返しのつけようがなく失敗してしまいます。
「ゴマが実に黒々と照った、ほんとうに例えようもないほど滑らかな泥状のものとなったところで、初めてぬるま湯を、少しづつ入れて、おしるこ程度の濃さ(といってもいくらか濃いめに)に、すりながらのばしていきます。」
それを鍋に移し、煮立てて、黒砂糖と塩少々で味をつけます。
火からおろし際に本葛をうすめにひいても好いようです。
中にいれるお餅は、ゴマじるこには焼いたものは合わないので、「ゆでて柔らかくなった、丁度ギュウヒのような感じの出たものがよくうつります」と書かれています。
「手つきの、本当によくついたお餅がのぞましく、更にぜいたくをいえば、つきたてのところを、そのまますぐ入れば、申し分はないのですが、そこまでは望めそうもありません。」
「よくうつる」という表現、これは「よく映る」で、調和がとれているという意味ですが、平塚らいてうらしいと思いました。
らいてうは、コーディネーションに敏感で、着るものをはじめ、色のつりあいとか調和にはこだわりのある、スタイリッシュな印象があります。
「ゴマじるこは、とても濃厚なもので、小豆じるこのように、たくさん頂けるものではありませんから、つけるお椀もどちらかといえば、小さめなものを選ぶ方がよろしいでしょう。しかし、この味を一度知ったものには、とても忘れられないものになるでしょう。」と文章は結ばれています。
(第4号 ゴマじるこの作り方より)
『青鞜』メンバーも『暮らしの手帖』に執筆
文中で平塚らいてうが、奥村と書いているのは、画家で指輪(指環、と言っています)も制作した奥村博史。平塚らいてうの生涯の伴侶です。
奥村博史とらいてうの出会いは、茅ヶ崎の南湖院。
南湖院で『青鞜』メンバーのひとり、尾竹紅吉(富本一枝)が療養生活を送っていたとき、見舞いに付き添ったらいてうは、そこでたまたま出会った藤沢出身の奥村と、お互いに一目惚れ。
奥村博史は、らいてうより5つ年下の21歳、絵描き志望でした。
『暮しの手帖』で、影絵作家の藤城清治のさし絵と共に、童話の文章を書いていた富本一枝が、初期の『青鞜』で活躍した尾竹紅吉と知って、私は少なからず驚きました。
若い頃、『青鞜』で数々の伝説的なスキャンダルを(新聞があること、ないこと書きたてたのですが)作りあげたメンバーが、こうして『暮しの手帖』に執筆を寄せているのって、時空を超えているような不思議さがあります。
・・・ということで、胡麻をとことん「する」作業は、ほとんど奥村博史だったようです。
菜食で玄米飯を好んだらいてうは、「陰陽の調和」のエッセイをこう結んでいます。
「いわゆるご馳走も時にはけっこうだが、わたくしの食卓に、いつもほんとうにほしいと思うものは、塩昆布、胡麻塩、鉄火味噌、小魚の佃煮。大根おろしと海苔くらいなものなのだから。」